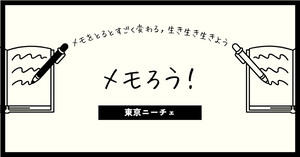
第1章: はじめに
1.1 なぜ“忘れる前提”が必要なのか
結論:私たちは「すべてを覚える」前提で生きているから、脳が疲れている。
現代社会は、覚えることが多すぎます。
- やることリスト
- 誰かの言葉
- スケジュール
- ふと浮かんだアイデア
すべてを脳に詰め込もうとすると、思考が渋滞し、行動が遅くなり、ストレスも増えていきます。
【P】問題:あれこれ思い出そうとするだけで疲れてしまう
【R】理由:脳を「記憶メモリ」扱いしてしまっているから
【E】例:メモをとるだけで頭がスッキリし、目の前のことに集中できたという声多数
【P】結論:「忘れてもいいから、書く」ことが、現代の最強戦略
1.2 人間の脳は「記録装置」ではない
結論:脳は“考える”ための装置。“覚える”のはメモの仕事。
もともと私たちの脳は、「記憶の倉庫」ではありません。
- 脳は重要でないことを忘れるようにできている
- 短期記憶は“たった7つ前後”しか保持できない
- 重要な情報ほど「外に出す」ことで長く活用できる
【P】問題:覚えておこうとするだけで、他の思考が止まってしまう
【R】理由:脳は“保持”と“創造”を同時にできないから
【E】例:アイデアを一度書き出したことで、次の発想が広がった
【P】結論:「書くこと」は、脳に“考える余白”をつくる行為
1.3 本記事の目的と読者が得られるもの
本記事では、以下のことをお伝えします。
- 「覚えなくてもいい」前提で人生をラクにする方法
- メモを“第二の脳”として使う技術と習慣
- 書いた情報を“活かす仕組み”に変えるステップ
読み終える頃には、「記憶しなきゃ」というプレッシャーから解放され、
書くことが“整えること”であり、“人生の加速装置”であることを実感していただけるでしょう。
第2章: 「外部脳」という考え方とは
2.1 外部脳とは「自分の代わりに覚えてくれる仕組み」
結論:「脳の代わりに記憶するメモ」は、“持ち歩ける頭脳”になる。
「外部脳」とは、ノートやアプリなどに思考や記憶を記録しておくことで、後から“取り出せる仕組み”をつくることです。
- 忘れても、見れば思い出せる
- アイデアが浮かんだ瞬間に書けば、あとで育てられる
- 情報を“保存”するだけでなく、“再び使える”状態にしておく
【P】問題:せっかくいいアイデアを思いついても、数時間後には忘れてしまう
【R】理由:脳内だけに留めておくのは不安定だから
【E】例:「あとで書こう」と思っていたアイデアが思い出せず後悔した経験は誰にもある
【P】結論:“覚えるため”ではなく、“取り出すため”にメモを取るのが外部脳思考
2.2 覚えるより“出せる”が重要な時代
結論:暗記より「検索・整理・活用」のほうが価値を持つ。
今や、情報は“記憶する”より“どう引き出すか”が問われる時代。
- Googleに聞けばすぐに答えが出る
- AIは即座に情報をまとめてくれる
- それでも自分の思考は「書いて出す」ことで深まる
【P】問題:たくさん知っているのに、活かせない
【R】理由:知識を取り出す「仕組み」が脳の中にないから
【E】例:自分のメモ帳を検索して、過去の自分の言葉から新しいアイデアを得た
【P】結論:情報は“覚えるもの”から“使いこなすもの”へと変わった
2.3 「記録=保存」から「記録=再利用」へ
結論:メモは“保管庫”ではなく“道具箱”であるべき。
メモを「とりあえず書いておくだけ」では、意味が半分です。
真に役立つのは、「後から使える形で残す」こと。
- タグやカテゴリーで整理する
- 日付や文脈とセットで書いておく
- 後日検索しやすい言葉を添えておく
【P】問題:書いたけど、どこに書いたかわからなくなる
【R】理由:書いた情報に“取り出しやすさ”がないから
【E】例:日付+キーワードでノートを整理したら、過去の気づきが次の資料に活きた
【P】結論:“メモ=再利用前提”で書くことで、知識は道具になる
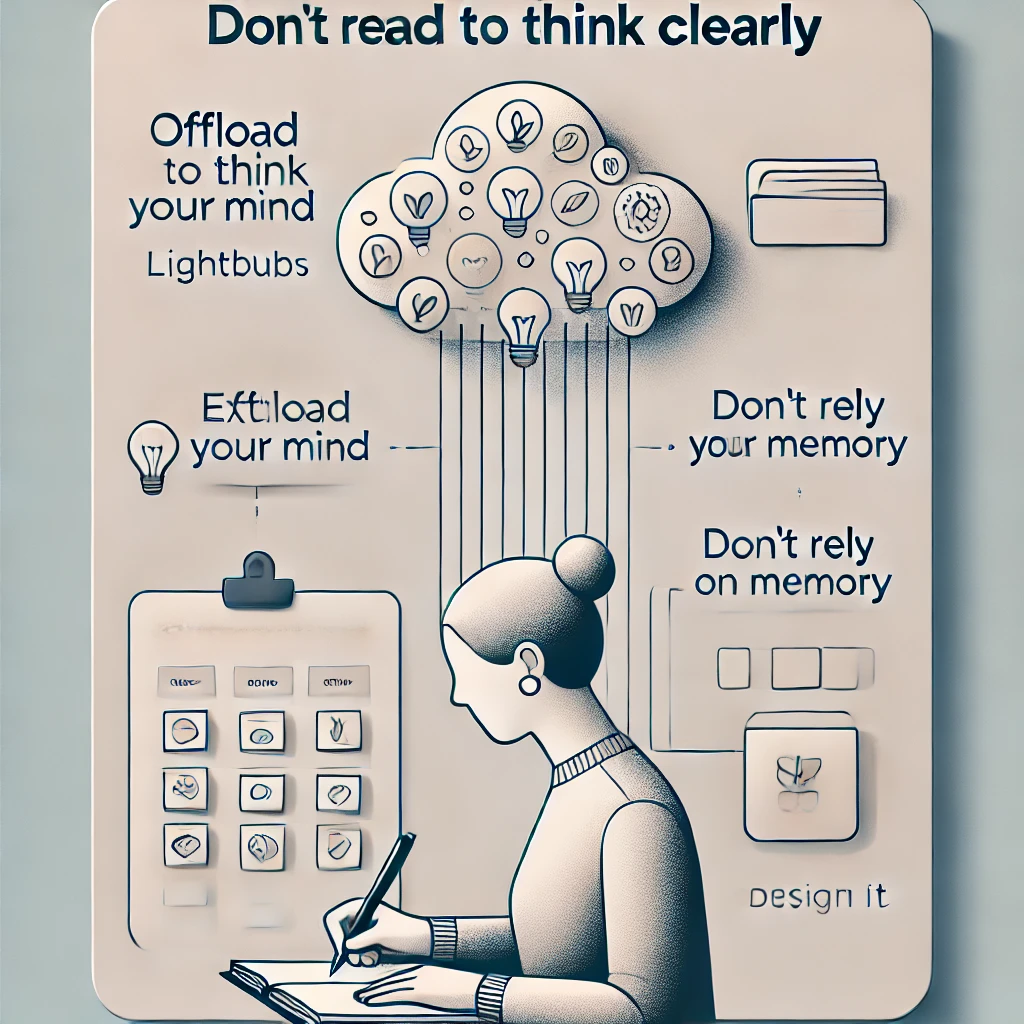
第3章: 忘れることは悪ではなく、むしろ武器になる
3.1 脳は「忘れることで賢くなる」仕組み
結論:脳は“忘れる”ことで、大事なことに集中できるようにできている。
脳は、何でもかんでも記憶しておくと思考が混乱するようにできています。
重要な情報を見極めるために、忘却というフィルターがあるのです。
- どうでもいい情報を勝手に捨てることで、脳は軽くなる
- 書き出して忘れると、“覚えなければ”という負荷から解放される
- 「覚えておかないと」と思うこと自体がストレスになる
【P】問題:全部を覚えようとして、逆に集中できなくなる
【R】理由:脳の“記憶容量”には限界があるから
【E】例:覚えることをやめてメモに任せたら、思考がクリアになった
【P】結論:忘れることは“思考の整理”であり、進化した機能
3.2 忘れるからこそ“選べる”ようになる
結論:全部覚えている人より、“必要なときに選び取れる人”が強い。
人間の強みは、「必要なときに、必要な情報を引き出す能力」。
外部脳を活用することで、膨大な情報の中から“今使えるもの”を選ぶことができるようになります。
- 書いた内容をすべて覚えていなくてもいい
- 大事なのは、「書いたことを探し出せる仕組み」
- 使いたいときに“取り出せる=活用できる”が重要
【P】問題:たくさんメモをとっているのに、結局何も使えていない
【R】理由:記録を“整理”して“選ぶ仕組み”がないから
【E】例:タグや日付でまとめておいたメモから、アイデアを再発掘できた
【P】結論:“忘れること”を前提に仕組みを整えれば、記憶に頼らず成果が出る
3.3 外部脳を使えば「創造的な思考」に集中できる
結論:「記憶」に使っていた脳のリソースを、「創造」に回せるようになる。
メモを使って“覚える労力”を外に逃がすことで、本来の脳の力=発想・決断・集中を取り戻せます。
- ToDoリストを外に出すと、「今やること」に集中できる
- アイデアメモを記録すると、「その続き」が生まれやすくなる
- 不安や悩みを書き出すと、「解決思考」に切り替わる
【P】問題:考えたいのに、頭の中が“気になることで埋まって”動けない
【R】理由:脳のメモリが雑念でいっぱいになっているから
【E】例:やることを全てメモに吐き出したあと、集中して仕事に取りかかれた
【P】結論:“忘れるために書く”ことで、創造力が最大化される
第4章: 外部脳としてのメモの実践法
4.1 書くべき情報は「思考・予定・記憶」の3つ
結論:「考えたこと」「これからのこと」「思い出すべきこと」をすべて書く。
外部脳としてのメモに書くべきは、以下の3ジャンルです。
- 思考(考えていること・アイデア・問題意識)
- 予定(タスク・約束・未来に関係すること)
- 記憶(記録・ログ・学んだこと)
これらをジャンルで分けて書くだけで、情報の取り出しやすさが飛躍的に上がります。
【P】問題:メモ帳がごちゃごちゃして何を書いたか分からなくなる
【R】理由:思考と記録と予定を同じ場所に混ぜているから
【E】例:ノートを3分類に分けてから、使い方が整理され、ミスも減った
【P】結論:「何のためのメモか?」を意識して書くだけで、整理力が高まる
4.2 アナログかデジタルか?使い分けのコツ
結論:メモには「速さ・感情・構造」のバランスが必要。
どちらを使うべきか迷ったときは、目的別に使い分けるのが最適です。
- アナログ:感情やひらめき、手を動かしながら考えたいとき
- デジタル:検索・整理・持ち歩きやすさが重視されるとき
実際は、「ノート+アプリ」などハイブリッド型の人が多いです。
【P】問題:紙かアプリか迷って、なかなか始められない
【R】理由:両者のメリット・デメリットを理解できていない
【E】例:仕事はデジタル、感情整理は手書きで分けると使いやすさが倍増
【P】結論:自分の脳に合った“道具の組み合わせ”が最強の外部脳になる
4.3 使い続けるための“3秒ルール”
結論:「書く・記録する」を習慣にするには“瞬発力”がカギ。
メモを外部脳にするには、「書こう」と思った瞬間に書ける仕組みが必要です。
そこで活躍するのが**「3秒ルール」**です。
- 「思いついたら、3秒以内に書く」
- 「3秒以内に開けるツールにだけ記録する」
- 「3秒で取り出せないなら、その場所は使わない」
【P】問題:いいことを思いついたのに、すぐ忘れてしまう
【R】理由:メモを取るハードルが高すぎる or 後回しにしているから
【E】例:メモアプリをウィジェット化してから、3倍の頻度で記録できるようになった
【P】結論:“すぐ書ける環境”が、最強の外部脳を支える基盤
第5章: 外部脳を活かす“見返しと再活用”テクニック
5.1 曜日ごとの「情報リフレッシュ」習慣
結論:メモは“定期的に眺める”ことで生き返る。
書いたまま放置されたメモは、**“死んだ情報”**になってしまいます。
そこでおすすめなのが、曜日ごとに見返すテーマを決めること。
例:
- 月曜:予定メモ(仕事のスケジューリング)
- 水曜:思考メモ(進行中の課題・問題整理)
- 金曜:感情メモ(今週の振り返りと自己ケア)
【P】問題:せっかく書いても、メモが役立っていない
【R】理由:見返す習慣がなく、記録が“埋もれて”しまっているから
【E】例:Googleカレンダーに「メモ振り返りリマインダー」をセットして運用に成功
【P】結論:“メモを使う前提で書く”には、見返す習慣が不可欠
5.2 書きっぱなしを防ぐ「リンク思考」
結論:メモ同士を“つなぐ”ことで、新たな意味が生まれる。
メモを「孤立した言葉」にしておくのはもったいない。
それを他の情報と“関連付ける”ことで、活用度が一気に高まります。
- 「→」で次の思考をつなぐ
- 「#タグ」で関連テーマをグループ化
- 「この話、〇月〇日のメモにも出てきた」と引用する
【P】問題:メモがバラバラで、まとまりがない
【R】理由:情報を“線”で結ぶ発想がないから
【E】例:アイデアメモ同士をつなげて企画書が一気に完成した
【P】結論:メモは“つなげるほど”、アイデアとしての価値が高まる
5.3 メモからアイデアを生む「連想メモ法」
結論:再活用のコツは、“ひとつのメモから複数の視点を引き出す”こと。
メモは、そのまま使うより“ひらめきの種”として使うと創造性が育ちます。
やり方:
- メモの1つのキーワードから連想を広げる
- 1つの事象に「なぜ?」「どうすれば?」と問いを重ねる
- メモに「次に何を書くか?」の一言を足しておく
【P】問題:メモを読み返しても、インスピレーションが湧かない
【R】理由:情報を“展開”させる意識がないから
【E】例:一文メモから、ブログ記事3本分のネタが生まれた
【P】結論:メモは“ひらめきを生む”装置としても使える
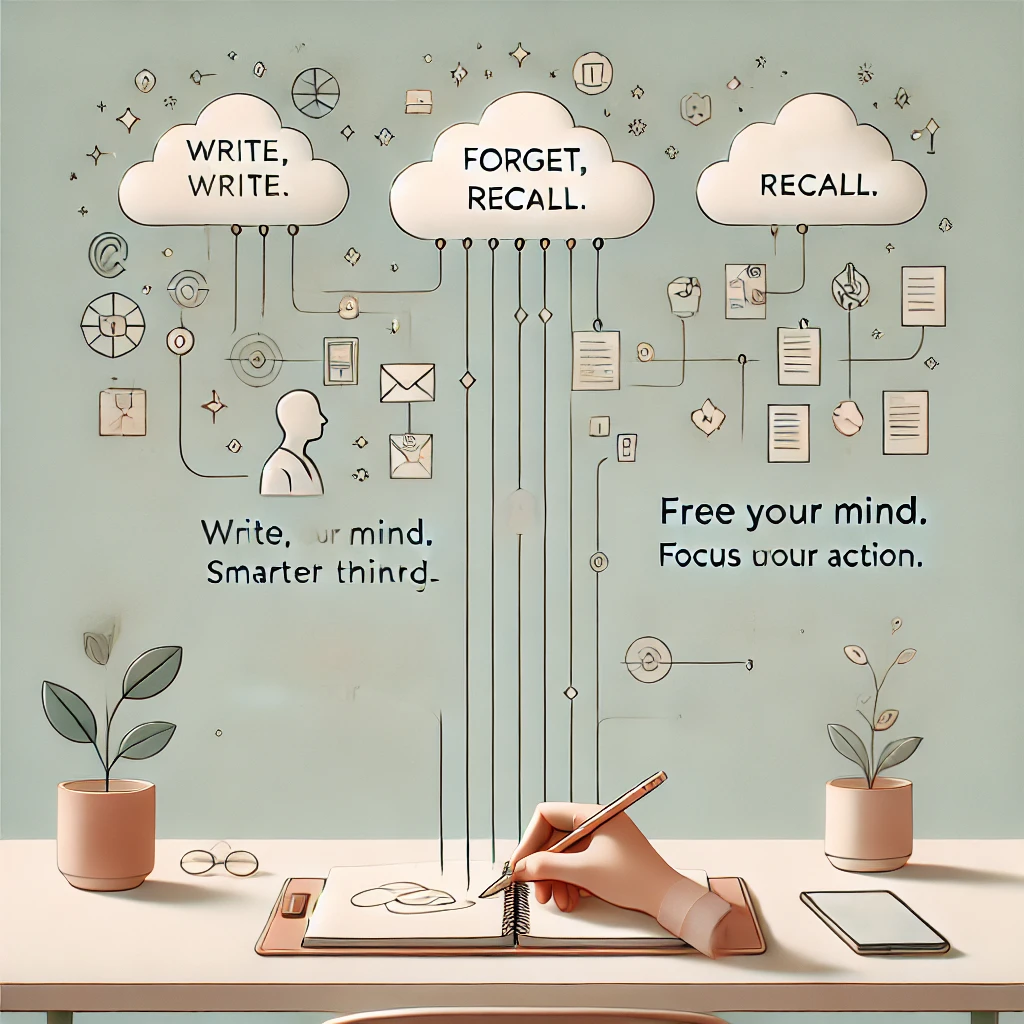
第6章: 外部脳を育てる3つのステージ
6.1 ステージ1:「書き出す」だけでOK
結論:まずは、“頭の外に出す”だけで十分。
最初のステージは、とにかく書くこと。
整理しなくていい、きれいに書かなくていい、ただ「思考・予定・記録」を外に出すことが目的です。
- 「忘れるために書く」から始める
- 書いた場所がバラバラでもOK
- 最初のゴールは「思考の渋滞解消」
【P】問題:最初から整理や体系化を目指して挫折する
【R】理由:完璧を求めて書くハードルが高くなるから
【E】例:紙切れでもスマホメモでも「とりあえず書く」を習慣にしたら、脳が軽くなった
【P】結論:書くことは“記憶”より先に、“思考を止めない道具”になる
6.2 ステージ2:「整理する」ようになる
結論:量が増えると、自分で“情報の住所”をつけたくなる。
書き出すことに慣れてくると、自然と「分けておきたい」「ラベルをつけたい」という感覚が湧いてきます。
このとき意識するのは:
- 思考メモ/行動メモ/ログメモの分類
- タグや見出しの活用(デジタル・紙いずれでも)
- 曜日・時期ごとにフォルダ分けする運用
【P】問題:書きっぱなしのメモが増えて、活用できなくなる
【R】理由:情報の“分類”がされていないから
【E】例:3つの色ペンを使ってジャンル別に分類したら、必要なメモがすぐに見つかるように
【P】結論:整理は“管理のため”ではなく、“使うため”にする
6.3 ステージ3:「つなげて使う」外部知能へ
結論:メモは“記録”ではなく“思考のネットワーク”になる。
最終的に、メモは点ではなく**「線でつながる思考の地図」**になります。
- アイデアと記録をつなげる
- 自分の思考パターンを可視化する
- メモから行動計画・創造的アウトプットへ発展させる
これは、「外部脳」から「外部知能」への進化です。
【P】問題:せっかく書いたのに、思考の役に立たない
【R】理由:メモが点で終わってしまっているから
【E】例:アイデアメモ→企画構想→行動チェックリスト→成果記録まで一貫して使えた
【P】結論:書く→整理→つなぐ、というステージを経て、“使える思考資産”ができあがる
第7章: まとめ ― 書いて忘れて、必要なとき呼び出せる人が強い
7.1 メモは“脳の補助輪”である
結論:メモは「思考・記憶・行動」を支える、静かなエンジン。
本当に賢い人は、「自分の脳を信じない人」です。
- 思い出せない前提で書く
- 忘れても大丈夫な仕組みを持っている
- 脳は“考えること”に集中できるようになる
【P】問題:「覚えておかないと」と緊張しすぎてストレスになる
【R】理由:脳を“すべての記憶装置”として使っているから
【E】例:メモを補助輪にしてから、「脳が走りやすくなった」と感じるように
【P】結論:メモは“覚えるため”ではなく、“自由に考えるため”の道具
7.2 忘れてもいいから、書き続ける
結論:メモは「思い出すために書く」のではなく、「考え直すために書く」。
忘れてもいい。
見返さなくてもいい。
書いたそのとき、思考が前に進んだなら、それが正解です。
- 書くことで感情が落ち着く
- 書くことで「次に何をするか」が明確になる
- 書くことで「自分と対話できる」ようになる
【P】問題:書いても意味がない気がして続かない
【R】理由:「見返さなきゃ意味がない」と思い込んでいるから
【E】例:書いたことを思い出せなくても、「あのとき書いたから落ち着けた」と感じる場面多数
【P】結論:“意味がなくても書く”が、“意味ある行動”に変わる瞬間をつくる
7.3 人生を変えるのは“覚えている人”ではなく、“書いて使える人”
結論:変化を起こせるのは、知識を“出力”できる人。
記憶力ではなく、「記録→再利用→行動」できる人が、人生を整えていきます。
- 書くことで気づきが生まれ
- 整理することで可能性が広がり
- 使うことで現実が変わる
【P】問題:インプットだけ増えて、何も変わらない日々が続く
【R】理由:記録と行動がつながっていないから
【E】例:小さなメモから行動が生まれ、1年で人生が大きく変わったという実例も多数
【P】結論:“覚える努力”をやめて、“書いて活かす力”を手に入れよう
🎁 今日からできる「忘れる前提」メモ習慣(テンプレート)
🧠 思考の書き出し:「今、気になっていることは?」
📝 予定の書き出し:「明日までにやるべきことは?」
📦 記録の書き出し:「今日覚えておきたいことは?」
※どれかひとつでもOK。たった1行で、脳が動き始めます。


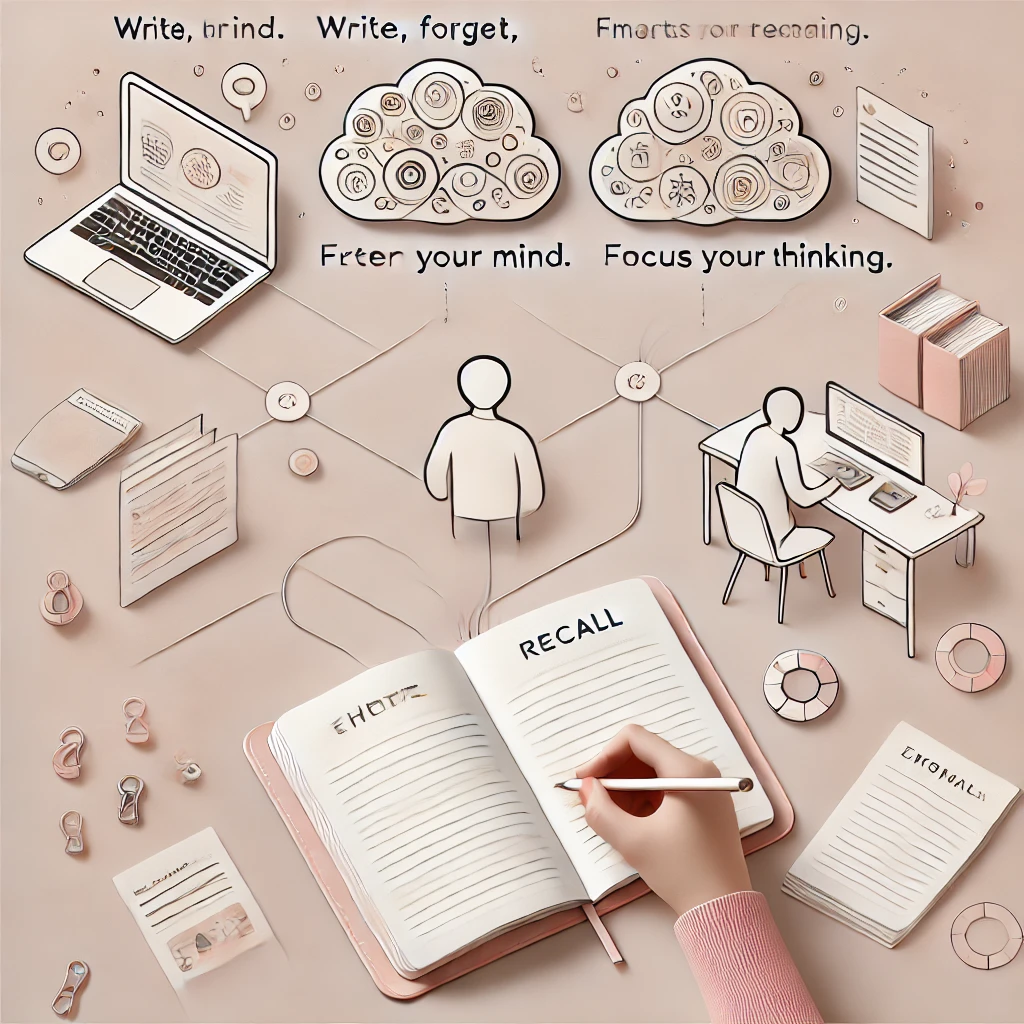
コメント