
叱ることもほめることも、上下関係をつくる行為である
名言「叱ることもほめることも、上下関係をつくる行為である。」
― アルフレッド・アドラー
■ ひとこと解説
対等な関係を築くことが、真の信頼関係の第一歩です。
「評価する立場」ではなく、「ともに歩む立場」へ。
■ 解説:「上下関係の心理」が信頼を遠ざける
アドラーは、家庭や職場、教育現場などで日常的に使われる「叱る」「ほめる」という行為に対して、
非常にユニークで深い視点を持っていました。
それはこういうことです:
叱ることで、「私はあなたより上だ」という立場を暗に示す。
ほめることで、「あなたはまだ評価される立場にある」と伝えてしまう。
つまり、どちらも相手と対等ではない関係性を前提にしているというのです。
■ なぜ「ほめること」も上下関係なのか?
「叱ること」は一見してわかりやすいかもしれません。
しかし、「ほめること」が上下関係になるというのは、意外かもしれません。
例:
- 「よくできたね、えらいね!」
- 「さすがだね!立派だ!」
これらの言葉には、“上から見て評価している”というニュアンスが含まれているのです。
アドラーは、「評価される関係」ではなく、
「対等に認め合う関係」こそが、人を成長させると説きました。
■ 対等な関係=共同体感覚の土台
アドラー心理学の最終的な目標は、「共同体感覚の育成」です。
それは、他者と「対等で、所属感と貢献感を持てる関係性」を築くこと。
叱られた人・ほめられた人が「上下」を感じてしまうと、
「自分はここにいていいのか?」という不安や劣等感を生みかねません。
それに対し、次のような言葉が、対等で信頼ある関係を育てます:
- 「ありがとう、助かったよ」
- 「あなたのおかげでうまくいった」
- 「一緒に考えてみようか」
■ 今日の気づき
大切なのは、「上からの評価」ではなく、「横のつながり」。
叱る・ほめる前に、「この言葉は相手にどう伝わるか?」を考えてみましょう。
あなたが発する一言が、
「信頼の距離を縮める」のか、「評価の壁をつくる」のか――
その違いが、関係性の未来を変えていきます。
■ 実践アイデア:「評価しないフィードバック」を使ってみよう
今日から、以下のような言葉を意識的に使ってみてください。
| 評価的な言葉 | 対等な言葉 |
|---|---|
| 「すごいね!」 | 「どうやってやったの?」(関心) |
| 「えらいね!」 | 「それって嬉しかった?」(共感) |
| 「よくできたね」 | 「一緒に頑張った成果だね」(協力) |
相手をコントロールしようとせず、
“ともに考える仲間”として接することが、信頼関係を育みます。
■ まとめ
アドラーのこの名言は、「叱る」「ほめる」その前に、
人とどう向き合いたいかを問いかけてくれます。
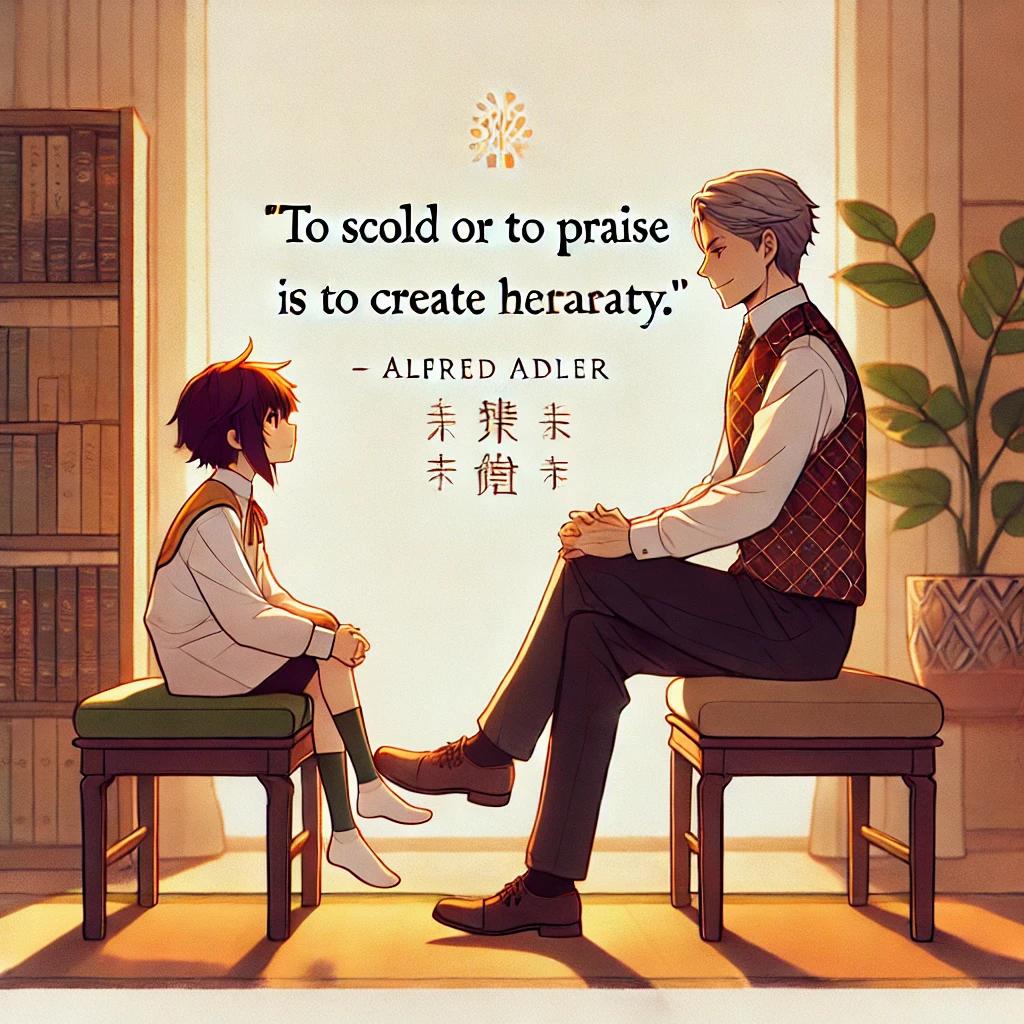

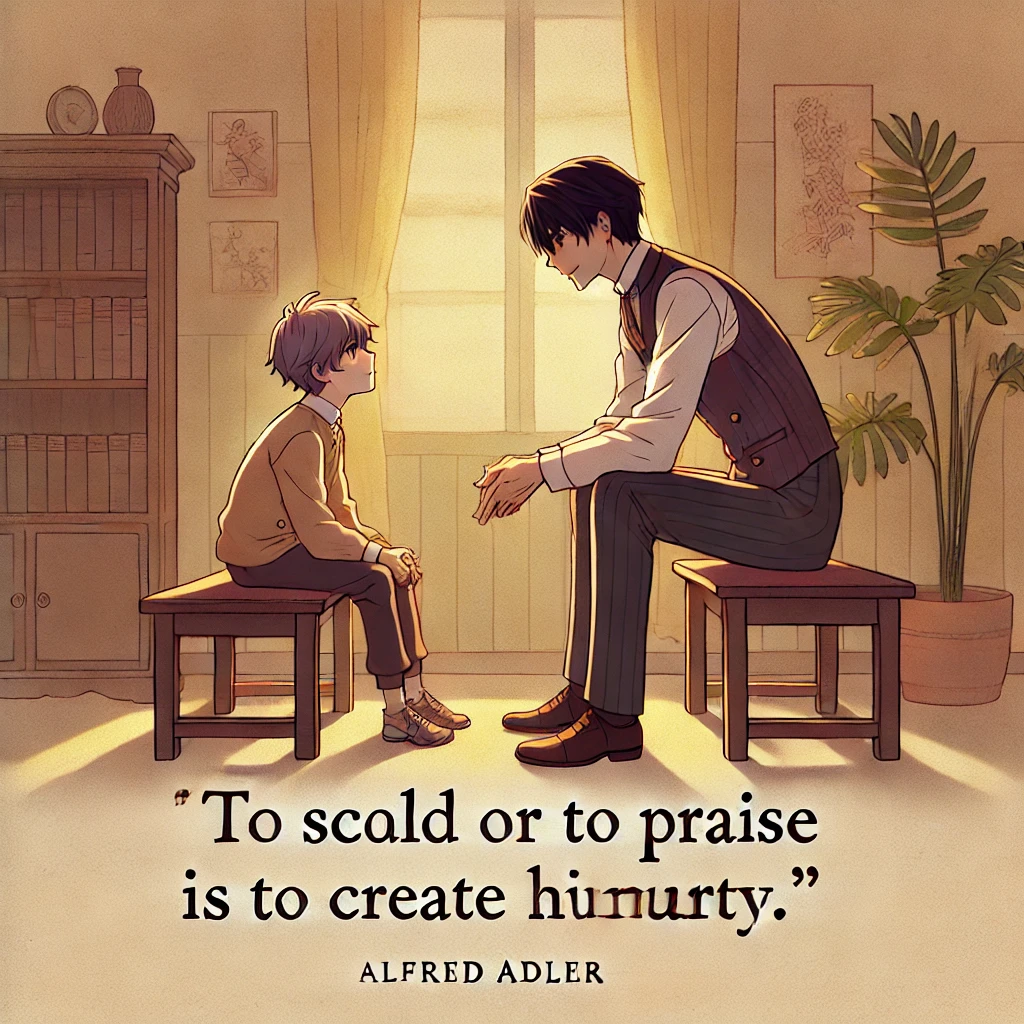
コメント