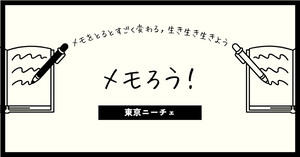
第1章: はじめに
1.1 なぜ「マイノート」が必要か?
結論:一冊のノートを自分専用の思考と行動の拠点にすることで、人生が整い、選択も感情も軽くなる。
忙しさや感情の揺れに振り回されず、自分らしいリズムを取り戻すためには、“頭の中”を整理し、“行動”や“気づき”を一元管理できる手段が必要です。
- 手帳だけでは感情や習慣は記録しきれない
- バレットジャーナルはタスク管理は得意でも、日常ログには弱い
- ライフログは気づきを拾うが、構造化が難しい
【P】問題:情報・時間・感情がバラバラで、人生の舵がブレがちになる
【R】理由:「使い分け」や「複数のノート管理」が負担になるから
【E】例:マイノートを使い始めてから、予定・感情・習慣を一冊で把握できるようになった
【P】結論:マイノートこそ、“自分の人生を整える最強ツール”になる
1.2 手帳術・バレットジャーナル・ライフログを統合する意味
結論:3つの強みを一冊に融合することで、管理と発見の両方が同時に得られる。
- 手帳術:時間と予定の軸
- バレットジャーナル:タスクとアイデアの構造化
- ライフログ:日々の感情や体調の記録
それぞれが強みを持っていても、分散させると続かない・見返せない・気づけないというジレンマに陥ります。
マイノートなら、それらを**“自分だけに必要な順序と形でまとめる”**ことができます。
【P】問題:複数ノートに分けるとストレスが増える
【R】理由:ノート間の移行や検索に手間がかかるから
【E】例:一冊に統合してから、書く習慣が続き、振り返りもしやすくなった
【P】結論:統合されたマイノートは、“使える情報”と“気づき”を一体化できる
1.3 本記事の目的と構成
本記事では、マイノートを初めて作る人でもスムーズに始められるよう、以下を丁寧に解説します:
- 基本構成と書き方(第2章)
- デザインやフォーマットの工夫(第3章)
- 習慣化のための実践テンプレート集(第4章〜第5章)
- 自分との対話と未来設計に活かす方法(第6章〜第7章)
読み終えた後は、1冊のノートで人生を「見える化」し、自分だけの軸を持った日々が始められます。
まだ持っていない方は、猫ちゃん柄でもシンプル黒でも良いので、ノートとペンを用意して進んでいきましょう。
第2章: マイノートの基本構成と書き方
2.1 コアページ:マンスリーログ・デイリーログ
結論:月・日軸で予定とタスクを管理することで、行動がブレず、感情も安定する。
- マンスリーログ:見開きで月間予定・目標・振り返りを記録
- デイリーログ:その日のタスク・メモ・感情などをシンプルに記録
これを一冊の中で固定化すると、見返しやすく続けやすい構造になります。
【P】問題:予定が飛び飛び・抜け落ちるのを繰り返してしまう
【R】理由:月間と日々の管理を分けることで把握が難しくなる
【E】例:常にノートの該当月ページを確認したら、抜けが格段に減った
【P】結論:月次×日次の流れは、マイノートの“骨組み”になる
2.2 コレクションページの作り方
結論:「これを残したい」「こうなりたい」モノを一箇所に集めると夢・気づき・情報が活きる。
- コレクションページとは、「やりたいことリスト」や「インスピレーション集」など、テーマごとの情報記録欄です。
- 書く時は、**見返す目的を定めて「インデックス」や「ページ番号でリンク」**すると効果アップ。
【P】問題:書きためたアイデアが埋もれて見返せない
【R】理由:テーマ別に分かれておらず、ノートの中で浮遊しているから
【E】例:「読みたい本」「旅行メモ」を章立て形式にしたら、活用頻度がUP
【P】結論:コレクションページは、あなたの“引き出し”として機能する
2.3 ライフログ要素(感情・体調・習慣)を加える
結論:日々の感情や体調、習慣を記録に残すことで、自己理解と調整力が高まる。
- 気分を色や記号でトラッキングする「気分トラッカー」
- 体調(睡眠・運動・食事)の記録
- 習慣チェックリスト(運動・瞑想・読書など)
これらを毎日の欄の余白に書くだけで、自分のリズムやパターンが自然と分かるようになります。
【P】問題:不調の原因が分からず、対応が後手になる
【R】理由:感情や生活習慣の変化に気づけないから
【E】例:気分トラッカーから「週のうち水曜は気分が下がりやすい」とわかり、対応策が取れた
【P】結論:人生を整えるには、気づきと記録のセットが鍵になる
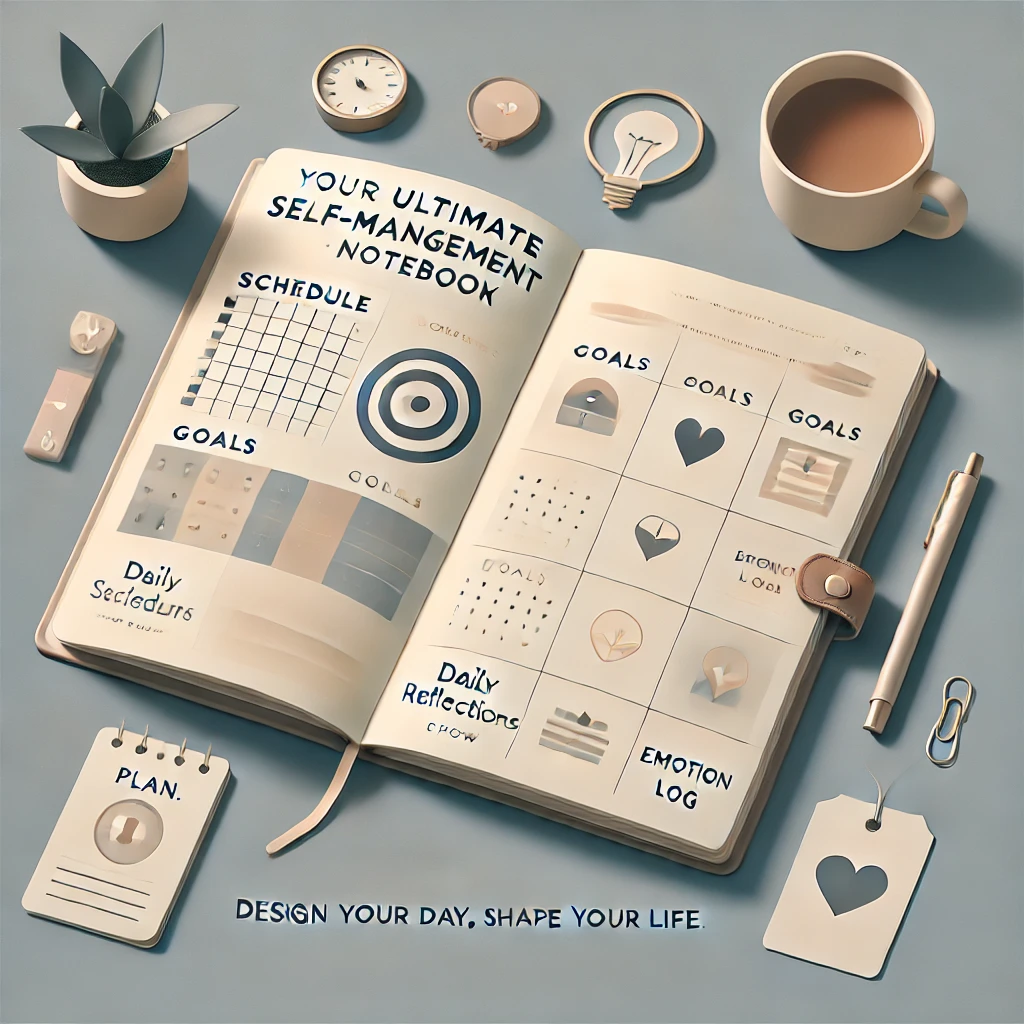
第3章: デザインとフォーマットの工夫
3.1 色使いとアイコンの取り入れ方
結論:見た目を楽しく整えるだけで、ノートを開く習慣が自然と身につく。
視覚から得られる情報は、モチベーションにも大きく関わります。
書きやすさだけでなく、「見ることが気持ちいい」という感覚を大切にすることで、ノートに向かうことが“ご褒美”のような時間になります。
【P】問題:ノートを書くことが義務になり、続かない
【R】理由:シンプルすぎて「書きたい」と思える感情が湧かないから
【E】例:気分ごとに色を変えたり、小さな猫ちゃんのシールを使ったことで、ノートタイムが癒しの時間に
【P】結論:カラーペン・アイコン・小さな装飾が、あなたの心をノートに向けてくれる
3.2 インデックスとページ番号の活用法
結論:必要なページをすぐ見つけられることで、書いたものが“資産”になる。
マイノートに多くの情報を記すほど、検索性が重要になります。
そのために役立つのが「インデックス(目次)」と「ページ番号」です。
- ノート冒頭2ページほどを「インデックス専用」に
- 各ページの右上に「ページ番号」を
- 新しい記録を始めたら、インデックスにも追加
【P】問題:せっかく書いたのに、必要なときに見つからない
【R】理由:記録が散らばっていてアクセス性が悪い
【E】例:毎月の目標ページをインデックスに追加したら、振り返りが劇的に効率化
【P】結論:書くだけでなく、見返せる構造が“マイノートを機能させる鍵”
3.3 付箋・ステッカー・クリップの実用テク
結論:情報の整理とアクセントに“遊び心”を加えることで、使いやすさと楽しさが両立できる。
文具は単なる装飾ではなく、**“情報整理の道具”**としても非常に優秀です。
- 付箋:移動可能なTODOやアイデア出し
- ステッカー:モチベーションUPや見出し代わりに
- クリップ:テーマ別ページの即アクセス用
【P】問題:書いた情報がごちゃついて管理がしにくい
【R】理由:可変情報と固定情報が混在しているから
【E】例:目標や願望のページに「星型ステッカー」を貼ると、それを見るだけで元気が出る
【P】結論:文具を“感情と情報のナビ”として活用すれば、ノートはもっとあなたらしくなる
第4章: 書き方別テンプレート集
4.1 朝のリセットページ
結論:1日を“自分の言葉”で始めることで、内面の主導権を握れる。
朝のページは、1日の始まりを整える「リセットの場」。
テンプレート例:
- 今日やること(3つだけ)
- 今日の気分(絵文字や色で)
- 今日のひとこと目標
【P】問題:朝のスタートがバタバタして、気持ちも乱れる
【R】理由:外部の情報(スマホやSNS)にいきなり触れているから
【E】例:朝のノートで「落ち着いてコーヒーを飲む」と書くだけで、1日が穏やかに始まった
【P】結論:“言葉で整える朝”が、その日の質を決める
4.2 週次レビュー&振り返り
結論:自分の成長や傾向に気づくことで、翌週への行動が明確になる。
週末に以下のような項目を記録します:
- できたこと・嬉しかったこと
- できなかったこと・モヤモヤ
- 今週の気づき・来週の改善策
【P】問題:なんとなく週が終わり、気づいたら何も変わっていない
【R】理由:振り返りがなく、自分の行動パターンを認識できていない
【E】例:毎週「金曜の夜」にレビューする習慣をつけたら、生活のリズムが安定した
【P】結論:振り返りは“次の一歩”を明確にするための儀式
4.3 月次の目標・進捗・感謝ログ
結論:月単位で目標設定・進捗確認・感謝を書くことで、心と行動の“軸”が育つ。
テンプレート例:
- 今月の目標(1〜3つ)
- 進捗チェック(週次で○×)
- 今月感謝したこと(10個)
【P】問題:忙しさに流されて、やりたいことが置き去りになる
【R】理由:長期視点を持つ機会がないから
【E】例:月末に「感謝したこと10個」を書いたら、自分の幸せに敏感になった
【P】結論:月単位の俯瞰と感謝が、未来をつくる“種”になる
第5章: メモの見直しと気づきの循環
5.1 書きっぱなしにしない習慣
書くだけで終わらせず、定期的に見返すことで「気づき」が深まります。
メモは「その場の感情の掃き出し」で終わることも多いですが、数日・数週間後に読み返すことで、当時の自分の状態を客観視することができます。
【P】問題:書いたことを読み返さず、ただ流れてしまう 【R】理由:忙しい日々の中で、振り返る時間を取るのが難しい 【E】例:毎週末に“見返しタイム”を10分設けたことで、悩みのパターンに気づけるようになった 【P】結論:メモは「書いて終わり」でなく、「見返して気づく」ことで価値が高まる
5.2 「過去の自分」との対話を通じて整理する
メモを通じて、過去の自分の声を聴き、今の自分とのズレを見つめる時間に。
文章にすることで、当時の感情が浮かび上がり、それと今の感覚を比較することで、心の成長や変化を確認できます。
- 数週間前に抱えていた悩みが、今では解決している
- 昔の夢が、まだ心に残っている
- 怒りの原因が、思ったより小さなことだった
こうした「内省」のヒントが、整理を助けます。
5.3 定期的な「書き直し」でアップデートする
過去の自分の言葉に今の視点を加えて書き直すことで、考えがより深まり、成長が記録される。
メモの中には「考えが浅かったな」と思える記録もあるでしょう。 そのときは、別のページに“書き直しメモ”として改めて綴るのが効果的です。
これは、自分自身の“更新履歴”をつくる行為。 書くことで、気づきのループが育ちます。

第6章: 本音メモを「生かす」ためのアイデア
6.1 キーワード化して心の傾向を知る
感情メモに出てきた言葉やテーマを分類することで、心の癖や関心が可視化される。
たとえば:
- よく出てくるキーワード:「疲れた」「頑張らなきゃ」「無理かも」
- 週に何度も登場するフレーズ:「〇〇のせいで」「どうせ自分なんて」
こうした語尾や語彙に注目することで、自分の“無意識の口ぐせ”や思考グセが見えてきます。
6.2 イライラ・モヤモヤ解消メモの定番フォーマット
手間を減らしつつ、しっかり感情に向き合える“型”を持つことで、毎日の継続がラクに。
おすすめの例:
- 今日のイライラ:〇〇
- その原因:△△
- 自分が本当に感じていたこと:□□
- そこから学べること:◇◇
このような“感情の因数分解”を習慣にすることで、心がラクになりやすくなります。
6.3 信頼できる人との「メモシェア」
ごく一部の信頼できる人に“見せる前提で”書いたメモは、対話の素材にもなる。
自分の中にある本音を、第三者に伝えるのは勇気がいりますが、メモという形があると「話の入口」になってくれます。
たとえば:
- カウンセラーとの対話前にメモを見せる
- 友人とのやりとりに「この間こんなこと書いた」と使う
メモがあると、気持ちをうまく言葉にできなくても、「気づいてもらう」きっかけになります。
第7章: まとめ ― 自分だけの場所が、心を整える
7.1 書くだけで、気持ちは整っていく
メモは、「誰かに見せるため」ではなく、「自分を知るため」に書くもの。 誰にも見られない空間だからこそ、素直な気持ちが出てきます。
言葉にすることで、心がほどける。それが“人に見せないメモ”の最大の力です。
7.2 SNS疲れを癒す“心の避難場所”
SNSは便利だけれど、心に知らぬ間にプレッシャーを与えるもの。 「いいね」や「フォロワー数」を気にしない、自分だけの安心空間が必要です。
メモは、その避難場所。 誰にも気をつかわず、評価もされず、ただ「今の自分」を受け止める場になります。
7.3 自分だけの言葉を取り戻す
ネットの中では、誰かの言葉に流されやすい。 だけど、**本当に大切なのは“自分の内側から出てくる言葉”**です。
「こんなこと書いても意味ないかも」と思う日も、ひとこと書くことで、少し気持ちが軽くなる。
メモは、あなた自身を整える“心の習慣”になります。


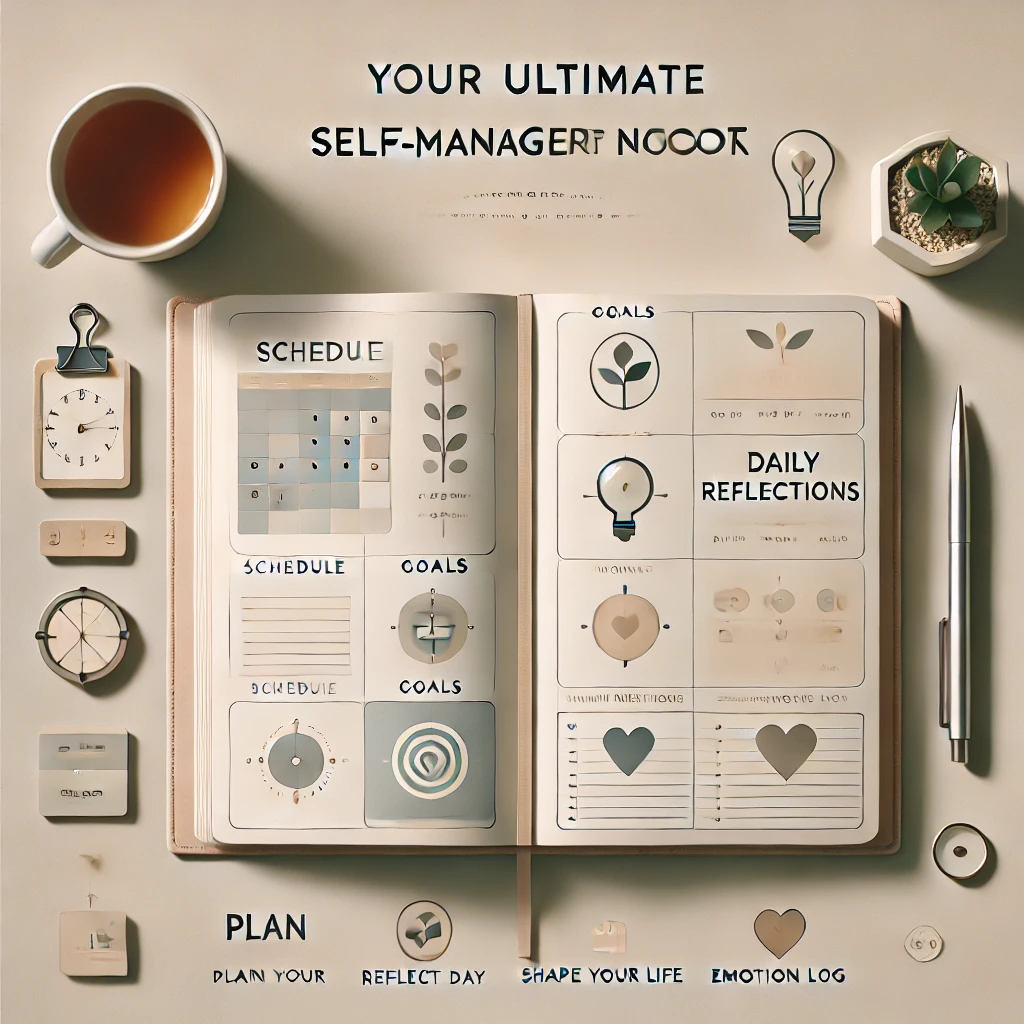
コメント